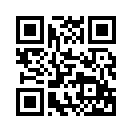2015年05月01日
京都うら〜らかハウス
今夜の宿泊は「京都うら〜らかハウス」
最近マンションをリニューアルして営業開始されたゲストハウスです。


この連休でお手軽なお宿がなかなか取れなかったのですが
なんとかお安く泊まれたところ。
ゲストハウスとはいうものの、きちんと個室に分かれているのでホテルとあまり変わらなかったです。
ちょっと水回りが残念だったかな
でも遅い到着の宿泊でしたし、フロントもその点自由がきいて大変助かりました。
ご飯を食べたあとは夜遊びせずにホテルへ直行。
明日明後日に備えて早目の就寝です
最近マンションをリニューアルして営業開始されたゲストハウスです。


この連休でお手軽なお宿がなかなか取れなかったのですが
なんとかお安く泊まれたところ。
ゲストハウスとはいうものの、きちんと個室に分かれているのでホテルとあまり変わらなかったです。
ちょっと水回りが残念だったかな

でも遅い到着の宿泊でしたし、フロントもその点自由がきいて大変助かりました。
ご飯を食べたあとは夜遊びせずにホテルへ直行。
明日明後日に備えて早目の就寝です

2015年05月01日
きっちん「きらく」
高速をビュンビュン飛ばして、無事京都に辿り着きました。
が、、、、昨夜から少しお鼻の調子が悪かった主人。
ハウスダストかと思いきや、どうやら風邪をひいてしまったようです
体調不良の為、夜食は京都の繁華街まで出る気力もなかったので
ホテルのすぐ近くの居酒屋で済ませることにしました。
 きっちん「きらく」
きっちん「きらく」

今夜のホテルのす〜ぐお近くのお店。
「うどん」というメニューに惹かれて入りました。
 お通し
お通し

 天婦羅盛り合わせ
天婦羅盛り合わせ

主人は暖かいおうどんを注文。私はにゅうめんを頂きました。

一見にゅうめんと九条ネギだけに思えますけど
一応にゅうめんの具に「えのき」が入ってます(笑)
白くて何がなんだかわかりません(^_^;)
飛び込みで入ったところでしたが、店長さんお一人で切り盛りされている
ほっこりとしたお店でした
が、、、、昨夜から少しお鼻の調子が悪かった主人。
ハウスダストかと思いきや、どうやら風邪をひいてしまったようです

体調不良の為、夜食は京都の繁華街まで出る気力もなかったので
ホテルのすぐ近くの居酒屋で済ませることにしました。
 きっちん「きらく」
きっちん「きらく」
今夜のホテルのす〜ぐお近くのお店。
「うどん」というメニューに惹かれて入りました。
 お通し
お通し
 天婦羅盛り合わせ
天婦羅盛り合わせ
主人は暖かいおうどんを注文。私はにゅうめんを頂きました。

一見にゅうめんと九条ネギだけに思えますけど

一応にゅうめんの具に「えのき」が入ってます(笑)
白くて何がなんだかわかりません(^_^;)
飛び込みで入ったところでしたが、店長さんお一人で切り盛りされている
ほっこりとしたお店でした

2015年05月01日
京都胡麻屋くれぇぷ堂さんの「胡麻はちみつ」
静岡での仕事は終わったあとは東京へ・・・
ではなく、反対方向の西へと車を走らせ、京都に向かっちゃいます
小腹が空いたので、途中のインターにておやつ。
 京都胡麻屋くれぇぷ堂
京都胡麻屋くれぇぷ堂

胡麻はちみつを二人で半分こしました。

京都に着く前から京都の味を堪能しています
ではなく、反対方向の西へと車を走らせ、京都に向かっちゃいます

小腹が空いたので、途中のインターにておやつ。
 京都胡麻屋くれぇぷ堂
京都胡麻屋くれぇぷ堂
胡麻はちみつを二人で半分こしました。

京都に着く前から京都の味を堪能しています

2015年05月01日
西富士宮散策
今朝は恐ろしい時間に出勤していった主人
午後から静岡で出張があるため、その前に片付けることがいっぱいなんだとか。
朝早くからお仕事ご苦労さまです。
お昼前に会社を出発。静岡まで車にて移動
私も便乗させて頂き西富士宮市にやって参りました〜

新茶の季節の茶畑、壮観な眺めです。
こんなにいいお天気ですが、残念ながら富士山は雲がかかってました
 いっぷく屋にて
いっぷく屋にて

 富士宮焼きそば
富士宮焼きそば

美味しい郷土料理を昼食に頂きました。
そして主人は取引先へ。私は一人この近辺をのんびりと散策です。
お近くなので立ち寄りました。
 富士山本宮・浅間大社(せんげんたいしゃ)
富士山本宮・浅間大社(せんげんたいしゃ)

「富士本宮浅間社記」によれば、第7代孝霊天皇の御代、富士山が大噴火をしたため、周辺住民は離散し、荒れ果てた状態が長期に及んだとあります。第11代垂仁天皇はこれを憂い、その3年(前27)に浅間大神を山足の地に祀り山霊を鎮められました。これが当大社の起源です。
その後は姫神の水徳をもって噴火が静まり、平穏な日々が送れるようになったと伝えられています。この偉大な御神徳は、万人の知るところとなり、篤い崇敬を集める事となりました。また、富士山を鎮めるため浅間大神をお祀りしたのは当大社が最初であり、全国にある浅間神社の起源ともなっています。
本宮の境内の広さは約17000坪、徳川家康公寄進の神殿、
楼門を中心とした御神域は御神徳の偉大さを物語っています。
 流鏑馬の銅像
流鏑馬の銅像

歴代武将の事跡も多数ありますが、中でも特に篤い崇敬を寄せたのは、源頼朝・北条義時・武田信玄勝頼親子・徳川家康でした。
源頼朝公は、建久4年(1193)富士山麓において巻狩りを行った際、流鏑馬を奉納されました。現在、流鏑馬祭としてとして伝えられています。

(HPより流鏑馬神事の写真)
社伝によると建久4年(1193)源頼朝が富士の裾野で巻狩を行った際、当大社に流鏑馬を奉納し武運長久・天下太平を祈願したことから始まるとされています。天正5年(1577)の『富士大宮御神事帳』、慶安3年(1650)の『富士本宮年中祭禮之次第』などにも記載されている800余年の伝統を持つ神事です。
流鏑馬自体は、5月5日に奉納されますが、これに先立ち様々な祭儀が行われます。これらは、本宮祭儀を行うための重要な意味を持っています。
 流鏑馬神事が行われる桜の馬場
流鏑馬神事が行われる桜の馬場

5月5日勇壮な神事流鏑馬式が執り行われる馬場です。馬場にはご神木の桜が植えられています。これらを含めて境内には500本以上の桜が植えられ、春には桜の名所として賑わいます。
5日の神事ももうすぐということで、足場を整えるために
新しい土砂が盛ってありました。
 楼門
楼門

楼門は、間口4間、奥行2間半、高さ6間半2階入母屋造で、正面・左右脇に扉が付きます。楼門の左右には随身が安置してあり背銘に慶長19年(1614)の年号があります。楼門に掲げる扁額は聖護院入道盈仁親王の御筆で文政2年に制作されたものです。
 鉾立石
鉾立石

楼門前の石段上にある自然石は鉾立石といい、明治初年まで行われていた山宮御神幸の際、神鉾を休め奉った所です。
 本殿と拝殿
本殿と拝殿

 桜の木
桜の木

本殿拝殿のすぐ横には立派な枝垂れ桜の木が。
きっと春には美しい見事な桜が咲き誇るに違いありませんね。
 藤棚
藤棚

今の季節は湧玉池のほとりに藤の花が満開でした。
 湧玉池
湧玉池

東脇門を出ると平安朝の歌人平兼盛が「つかうべきかずにをとらん浅間なる御手洗川のそこにわく玉」と詠じた湧玉池があります。この池は富士山の雪解け水が何層にもなった溶岩の間を通り湧出するもので、特別天然記念物に指定されています。 清水の湧出する水源の岩上には朱塗優雅な水屋神社があります。富士山登山者はこの霊水に禊ぎをして登山する古くからの習わしがあります。
《青字は全てHPより引用》
 美しい水面
美しい水面

キラキラと輝いていました


境内の椅子に座ってのーんびりと。
初夏の爽やかな風に吹かれながら、木陰にて暫しゆったりと時を過ごしました。
本日は1日ということで近隣では「朔日詣(ついたちもうで)」も実施中

こちらは最近始まった地域のイベントだそうです。

 江戸屋にてコーヒータイム
江戸屋にてコーヒータイム

一杯200円のセルフサービスタイプの喫茶でした。

喫茶内でこれまたのんびりのんびり。
本などを眺めながらまったりと過ごしました。
流鏑馬神事に由来して「流鏑馬サブレ」も販売されていましたよ。

夕方、仕事の終わった主人と合流。
先程の広場内で気になっていたジェラート屋さんに寄りました。

いろいろなジェラートが・・・・

中でも一番気になるのは「朔日詣限定ジェラート・富士宮やきそば」

一体どんな味がするのかしら???
(いや、やきそば・・・なんとなく想像も出来たり?? )
)
限定に弱い私はちょっとばかり揺らいでしまいましたが、
結局無難なジェラートにすることに
 「チョコレート」と「特選ミルク」
「チョコレート」と「特選ミルク」

でも実は特選ミルクの一部に「富士宮やきそばジェラート」が少しだけプラス。
店員さんが間違えて特選ミルクの上にダブルで富士宮やきそば味を入れようといてくれていて
「違います違います 」と言って退けてもらったものの
」と言って退けてもらったものの
ぬぐいきれなかったジャラートが少しばかり
ちょっと得したような?
一応富士宮やきそばジェラートには青のりトッピング
ということで、しっかりその部分に青のりをふりふり。
三種のお味を楽しみました。満足満足

午後から静岡で出張があるため、その前に片付けることがいっぱいなんだとか。
朝早くからお仕事ご苦労さまです。
お昼前に会社を出発。静岡まで車にて移動

私も便乗させて頂き西富士宮市にやって参りました〜


新茶の季節の茶畑、壮観な眺めです。
こんなにいいお天気ですが、残念ながら富士山は雲がかかってました

 いっぷく屋にて
いっぷく屋にて
 富士宮焼きそば
富士宮焼きそば
美味しい郷土料理を昼食に頂きました。
そして主人は取引先へ。私は一人この近辺をのんびりと散策です。
お近くなので立ち寄りました。
 富士山本宮・浅間大社(せんげんたいしゃ)
富士山本宮・浅間大社(せんげんたいしゃ)
「富士本宮浅間社記」によれば、第7代孝霊天皇の御代、富士山が大噴火をしたため、周辺住民は離散し、荒れ果てた状態が長期に及んだとあります。第11代垂仁天皇はこれを憂い、その3年(前27)に浅間大神を山足の地に祀り山霊を鎮められました。これが当大社の起源です。
その後は姫神の水徳をもって噴火が静まり、平穏な日々が送れるようになったと伝えられています。この偉大な御神徳は、万人の知るところとなり、篤い崇敬を集める事となりました。また、富士山を鎮めるため浅間大神をお祀りしたのは当大社が最初であり、全国にある浅間神社の起源ともなっています。
本宮の境内の広さは約17000坪、徳川家康公寄進の神殿、
楼門を中心とした御神域は御神徳の偉大さを物語っています。
 流鏑馬の銅像
流鏑馬の銅像
歴代武将の事跡も多数ありますが、中でも特に篤い崇敬を寄せたのは、源頼朝・北条義時・武田信玄勝頼親子・徳川家康でした。
源頼朝公は、建久4年(1193)富士山麓において巻狩りを行った際、流鏑馬を奉納されました。現在、流鏑馬祭としてとして伝えられています。

(HPより流鏑馬神事の写真)
社伝によると建久4年(1193)源頼朝が富士の裾野で巻狩を行った際、当大社に流鏑馬を奉納し武運長久・天下太平を祈願したことから始まるとされています。天正5年(1577)の『富士大宮御神事帳』、慶安3年(1650)の『富士本宮年中祭禮之次第』などにも記載されている800余年の伝統を持つ神事です。
流鏑馬自体は、5月5日に奉納されますが、これに先立ち様々な祭儀が行われます。これらは、本宮祭儀を行うための重要な意味を持っています。
 流鏑馬神事が行われる桜の馬場
流鏑馬神事が行われる桜の馬場
5月5日勇壮な神事流鏑馬式が執り行われる馬場です。馬場にはご神木の桜が植えられています。これらを含めて境内には500本以上の桜が植えられ、春には桜の名所として賑わいます。
5日の神事ももうすぐということで、足場を整えるために
新しい土砂が盛ってありました。
 楼門
楼門
楼門は、間口4間、奥行2間半、高さ6間半2階入母屋造で、正面・左右脇に扉が付きます。楼門の左右には随身が安置してあり背銘に慶長19年(1614)の年号があります。楼門に掲げる扁額は聖護院入道盈仁親王の御筆で文政2年に制作されたものです。
 鉾立石
鉾立石
楼門前の石段上にある自然石は鉾立石といい、明治初年まで行われていた山宮御神幸の際、神鉾を休め奉った所です。
 本殿と拝殿
本殿と拝殿
 桜の木
桜の木
本殿拝殿のすぐ横には立派な枝垂れ桜の木が。
きっと春には美しい見事な桜が咲き誇るに違いありませんね。
 藤棚
藤棚
今の季節は湧玉池のほとりに藤の花が満開でした。
 湧玉池
湧玉池
東脇門を出ると平安朝の歌人平兼盛が「つかうべきかずにをとらん浅間なる御手洗川のそこにわく玉」と詠じた湧玉池があります。この池は富士山の雪解け水が何層にもなった溶岩の間を通り湧出するもので、特別天然記念物に指定されています。 清水の湧出する水源の岩上には朱塗優雅な水屋神社があります。富士山登山者はこの霊水に禊ぎをして登山する古くからの習わしがあります。
《青字は全てHPより引用》
 美しい水面
美しい水面
キラキラと輝いていました



境内の椅子に座ってのーんびりと。
初夏の爽やかな風に吹かれながら、木陰にて暫しゆったりと時を過ごしました。
本日は1日ということで近隣では「朔日詣(ついたちもうで)」も実施中


こちらは最近始まった地域のイベントだそうです。

 江戸屋にてコーヒータイム
江戸屋にてコーヒータイム

一杯200円のセルフサービスタイプの喫茶でした。

喫茶内でこれまたのんびりのんびり。
本などを眺めながらまったりと過ごしました。
流鏑馬神事に由来して「流鏑馬サブレ」も販売されていましたよ。

夕方、仕事の終わった主人と合流。
先程の広場内で気になっていたジェラート屋さんに寄りました。

いろいろなジェラートが・・・・

中でも一番気になるのは「朔日詣限定ジェラート・富士宮やきそば」

一体どんな味がするのかしら???

(いや、やきそば・・・なんとなく想像も出来たり??
 )
)限定に弱い私はちょっとばかり揺らいでしまいましたが、
結局無難なジェラートにすることに

 「チョコレート」と「特選ミルク」
「チョコレート」と「特選ミルク」
でも実は特選ミルクの一部に「富士宮やきそばジェラート」が少しだけプラス。
店員さんが間違えて特選ミルクの上にダブルで富士宮やきそば味を入れようといてくれていて
「違います違います
 」と言って退けてもらったものの
」と言って退けてもらったもののぬぐいきれなかったジャラートが少しばかり

ちょっと得したような?
一応富士宮やきそばジェラートには青のりトッピング

ということで、しっかりその部分に青のりをふりふり。
三種のお味を楽しみました。満足満足