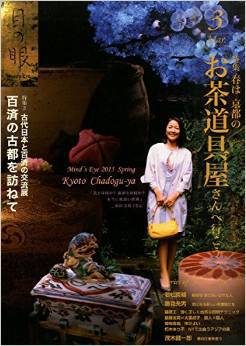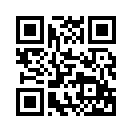2015年01月31日
京都清水寺・仁々木さんのコロッケ
帰りに海老名SAにて仁々木さん発見しました

お惣菜がずらり

 近江牛100%コロッケ
近江牛100%コロッケ

 ニニギ名物・最中コロッケ
ニニギ名物・最中コロッケ

コロッケが最中に挟まれていて、中に白味噌と黒豆トッピングされています。
すご〜い。
最中の食感がパリパリ。なかなか新鮮なお味でした。
夕食用に唐揚げを購入

箱根帰りに思いがけず京都に寄れたみたいな
楽しい旅でした。


お惣菜がずらり


 近江牛100%コロッケ
近江牛100%コロッケ
 ニニギ名物・最中コロッケ
ニニギ名物・最中コロッケ
コロッケが最中に挟まれていて、中に白味噌と黒豆トッピングされています。
すご〜い。
最中の食感がパリパリ。なかなか新鮮なお味でした。
夕食用に唐揚げを購入


箱根帰りに思いがけず京都に寄れたみたいな

楽しい旅でした。
2015年01月31日
強羅温泉・その2
おはようございます。清々しい朝を迎えております
お部屋の窓の障子を開けたら、こんなに素敵な風景が広がっていました

箱根の大文字
なんかいいですねっ (京都っぽい)
(京都っぽい)
毎年8月16日の夜には箱根強羅夏まつり・大文字焼が行われるのだそうです。
でもこの冬景色の大文字、よ〜く見ると「犬 」という字に見えるのは私だけでしょうか???(^_^;)
」という字に見えるのは私だけでしょうか???(^_^;)

たまたま雪の具合がそうさせているだけですよね
強羅温泉にもゆるキャラがいるらしい。
 ごうらん
ごうらん

朝風呂をまた貸切でいただいて 、お風呂上りのアイスもちゃっかり
、お風呂上りのアイスもちゃっかり

今日はプリンのアイスを頂きました。
今回のお宿は「旅庵 香音」

一泊お世話になりました。ありがとうございました。
この強羅の地域。地図でみるとなんてことはない感じがしたのですが
実際に行ってみるとかなりすごいアップダウンでビックリしました
恐るべし強羅
この「強羅」という地名には三つの説があるんだとか。
まず、①<ゴロゴロ ゴーラ説>
強羅は、早雲山の山裾にひろがる岩石の堆積で出来た傾斜地で、
大きな岩が”ゴロゴロ”していたことから「ゴーラ」となったという説
次に、②<亀の甲羅似説>
山の木々囲まれた姿が亀の甲羅に似ていたからという説
最後に、③<梵語説>
梵語で「石の地獄」という意味から取ったことという説
どの説にしてもこの地域は〝岩〟がキーワードのようですね。
 強羅公園
強羅公園

折角強羅に参りましたので、午前中はこの地域を散策することに。
強羅公園は強羅に大正3年(1914年)に開園された、日本初のフランス式整型庭園です。
フランス式整型庭園とは、平坦で広大な敷地に左右対称に幾何学的に池などを配置した特徴がありますが、強羅公園は傾斜面に作られています。
広い空と山々に囲まれた開放的な園内には、様々な花が植えられており、花の名所でもあります。
また、熱帯植物館や茶室、体験工房などの施設もあり、いろいろな体験を一度にできるのが魅力です。
 熱帯植物園・ハーブ園
熱帯植物園・ハーブ園

なんとも色鮮やかな美しい花が咲いていました。

マンゴー・・・と書いてあったけれど。。。。ほんと??

ベンチの周りにはお花がいっぱい

 ブーゲンビレア館
ブーゲンビレア館

シーサーの上にも(偶然?)花びらが・・・

少しおすまし顔に見えるシーサーくん
 ハイビスカス
ハイビスカス

 白雲洞茶苑
白雲洞茶苑

白雲洞茶苑は、箱根強羅の巨岩怪石の間に、深山のおもむきを保存して、見るからに山家の風情の濃い茶室群です。 ここは大正時代のはじめ、利休以来の茶人と称された鈍翁・益田孝(三井コンツェルンの設立者で男爵)によってはじめられ、特に白雲洞は、翁の創案になる田舎家の席として貴重な茶室とされています。 大正11年(1922)、この茶苑は三渓・原富太郎(横浜の富豪で美術品収集家として著名)に譲られ、この時三渓はあらたに対字斎を増築しました。 昭和15年(1940)、茶苑は再び原家より耳庵松永安左衛門(電力界の重鎮、松永コレクション創設者)に贈られ、こうして茶室は、明治・大正・昭和と3代を代表する3人の茶人の間に伝えられてきたものです。

近代数奇者茶人の間に流行した「田舎家の席」の」先駆的な作例で、山あいに農家の古材の持ち味を生かしながら、八畳敷の茶室を構成しています。 「いろり」に縁無しの畳という意匠は、ここで用いられる茶道具の見立てに、全く枠をはずし、自由なものにしました。床柱は、松永耳庵時代のもので、千年 を経た奈良当麻寺で使われていた古材です。
 お軸
お軸

 茶席ご観料(内部ご見学料)・点茶券付き(お菓子とも) 500円
茶席ご観料(内部ご見学料)・点茶券付き(お菓子とも) 500円


茶室は襖も空いていて、ほとんど外っという感じだったのですが
お席の毛氈の下にホットカーペットが敷いてあり
じっと座っているとじ〜んわりと暖かさが伝わってきてほっこりとしました。
 対字斎(居堂を兼ねた茶室)
対字斎(居堂を兼ねた茶室)

二代目の庵主、三渓原富太郎の作った席で、広縁の正面に「大文字山」の大の字が望まれ、鈍翁筆の対字斎の額がかかげられています。八畳に四畳の立水屋が付属します。
明治年間から開始された箱根登山鉄道(当時は小田原電気鉄道)による強羅地区の開発には、三井物産・益田鈍翁の絶大な協力がありました。 時の社長・草郷清四郎は強羅公園が完成した大正3年(1914)この恩に報いるため園内に翁の好む景勝の地を提供し、翁はここに奇岩を活用した浴室、白鹿 湯と野趣に満ちた茶室二庵をいとなみました。大正11年(1922)鈍翁はかねてより交流のあった原三渓にこの茶室を譲り、三渓はここに対字斎を新造しました。 三渓が逝った翌昭和15年(1940)三渓未亡人の希望によりこれら三席は松永耳庵に贈られ、これにより鈍翁・三渓・耳庵という偉大な茶人であり、明治・ 大正・昭和の日本経済に大きな役割を果たした稀代の経済人たちの遺構がここ強羅公園に現存することになりました。
(強羅公園・白雲洞HPより)
 強羅公園のシンボルともいえる噴水
強羅公園のシンボルともいえる噴水

雪景色の公園も素敵です。
庭園散策ですっかり身体も冷えきってしまったので、ここらで喫茶店へ

 Cafe Pic店内
Cafe Pic店内

 かぼちゃスープ
かぼちゃスープ

暖かいスープを頂きました。
 強羅のお土産に石川菓子舗さんの「強羅もち」
強羅のお土産に石川菓子舗さんの「強羅もち」


柚子の香りが効いて、とても美味しいお菓子でした
お餅の中の黒いもの。お豆のように見えますが小さくきざんだ羊羹でした。
そのあとはお近くの富士屋ホテルへ
 富士屋ホテル・花御殿
富士屋ホテル・花御殿

 富士屋ホテル・本館
富士屋ホテル・本館


富士屋ホテルは・・・
明治11年(1878年)7月15日、日本で始めての本格的なリゾートホテルとして開業しました。
多くの方が、ホテルの名前を聞いて最初に思い浮かぶのが「富士山」でしょう。残念ながら、ホテルから富士山を見ることは出来ません。しかし、富士山が外国人にとっての美の象徴であることを受け、かつてこの地で500年もの歴史を持っていた温泉旅館「藤屋」の名前をもとに「富士屋ホテル」と名付けられました。
明治16年の宮ノ下大火により、ホテルの原形とともに、6年間の記録も失われました。
しかしその1年後には見事に復興を果たし、今も変わらず、箱根に流れる時を見守り続けています。
よくテレビでも紹介されるところなので、一度訪れてみたかった場所です
 ホテルフロントでお出迎えしてくれたオリジナルテディベア
ホテルフロントでお出迎えしてくれたオリジナルテディベア

富士屋ホテル創業130周年を記念して作られたホテルの新しいマスコット
富士屋ホテルのベルボーイの制服を着用した愛らしいテディベアなんだそうです。
帽子、ベスト、ネクタイまで、すべて本物の制服を忠実に再現してあり、脱着が可能な可愛らしいぬいぐるみでした。
 フロント前の様子
フロント前の様子


ロビーへと向かう階段を上がると目に飛び込んでくるのが、なんとも印象的な飴色に磨かれた大階段。その横には、こちらも見事な一枚板の大きな彫刻があります。
実は、ここはかつてフロントカウンターがあった場所で、 この彫刻は、源頼朝が富士の巻狩りを興じる様子を描いたもので、細部まで見事に表現されています。
そして上を見上げると、柱には白い尾長鶏の彫刻が。かつてご来館されたヘレンケラー氏とともに写真に納まったこともある、富士屋ホテルの人気者でした。現在は彫刻となり、ホテルを見守り続けてくれています。
どれもはっとする程素晴らしいものばかりで目を奪われました
 ランチはレストラン「ザ・フジヤ」にて
ランチはレストラン「ザ・フジヤ」にて

(お店のHP掲載のレストラン全景 )
)


素晴らしい彫刻の数々に格天井、天井下の無数の絵画。
80年間変わらないクラシカルな空間が広がります
足元へ目を移すと何やら不思議なものが・・・

「トーテムポール???」かと思ってしまいましたが(^_^;)
こちら3代目・山口正造さんのお顔を模したレリーフが掘り込まれています。
この「ザ・フジヤ」への思い入れが強く、更にスタッフへの教育にも熱心だった正造さんが、スタッフがきちんと働いているか見張っているとも言われているのだとか
全ての柱の下に刻まれていました。
ランチタイムに大人気の「ビーフカレー」を頂きました。
 まずはピクルス
まずはピクルス

箱根伝統工芸の寄木細工で作られた専用の器にピクルスなど6種類が盛られていました。
付け合せもどれも美味 さすがは天下の富士屋ホテルです。
さすがは天下の富士屋ホテルです。
 ビーフカレー
ビーフカレー

ご飯にかけて、いっただきまーす。


とってもフルーティーなコクのあるお味でした
優雅なランチタイムを満喫いたしました。
伝統ある富士屋ホテルを堪能したあとは御殿場方面へ
晴天でしたので美しい富士山の眺めに期待していましたが、
このようにあいにく雲がかかってました〜

でもお買いものをしていたら段々に雲も流れていき

夕暮れ時にはこんなに素晴らしい光景に

もう少し長居したかったのですが、夜は予定があったため早めに切り上げ。
また是非遊びに行けたらと思います。

お部屋の窓の障子を開けたら、こんなに素敵な風景が広がっていました


箱根の大文字

なんかいいですねっ
 (京都っぽい)
(京都っぽい)毎年8月16日の夜には箱根強羅夏まつり・大文字焼が行われるのだそうです。
でもこの冬景色の大文字、よ〜く見ると「犬
 」という字に見えるのは私だけでしょうか???(^_^;)
」という字に見えるのは私だけでしょうか???(^_^;)
たまたま雪の具合がそうさせているだけですよね

強羅温泉にもゆるキャラがいるらしい。
 ごうらん
ごうらん
朝風呂をまた貸切でいただいて
 、お風呂上りのアイスもちゃっかり
、お風呂上りのアイスもちゃっかり
今日はプリンのアイスを頂きました。
今回のお宿は「旅庵 香音」

一泊お世話になりました。ありがとうございました。
この強羅の地域。地図でみるとなんてことはない感じがしたのですが
実際に行ってみるとかなりすごいアップダウンでビックリしました

恐るべし強羅

この「強羅」という地名には三つの説があるんだとか。
まず、①<ゴロゴロ ゴーラ説>
強羅は、早雲山の山裾にひろがる岩石の堆積で出来た傾斜地で、
大きな岩が”ゴロゴロ”していたことから「ゴーラ」となったという説
次に、②<亀の甲羅似説>
山の木々囲まれた姿が亀の甲羅に似ていたからという説
最後に、③<梵語説>
梵語で「石の地獄」という意味から取ったことという説
どの説にしてもこの地域は〝岩〟がキーワードのようですね。
 強羅公園
強羅公園
折角強羅に参りましたので、午前中はこの地域を散策することに。
強羅公園は強羅に大正3年(1914年)に開園された、日本初のフランス式整型庭園です。
フランス式整型庭園とは、平坦で広大な敷地に左右対称に幾何学的に池などを配置した特徴がありますが、強羅公園は傾斜面に作られています。
広い空と山々に囲まれた開放的な園内には、様々な花が植えられており、花の名所でもあります。
また、熱帯植物館や茶室、体験工房などの施設もあり、いろいろな体験を一度にできるのが魅力です。
 熱帯植物園・ハーブ園
熱帯植物園・ハーブ園
なんとも色鮮やかな美しい花が咲いていました。

マンゴー・・・と書いてあったけれど。。。。ほんと??

ベンチの周りにはお花がいっぱい

 ブーゲンビレア館
ブーゲンビレア館
シーサーの上にも(偶然?)花びらが・・・


少しおすまし顔に見えるシーサーくん
 ハイビスカス
ハイビスカス
 白雲洞茶苑
白雲洞茶苑
白雲洞茶苑は、箱根強羅の巨岩怪石の間に、深山のおもむきを保存して、見るからに山家の風情の濃い茶室群です。 ここは大正時代のはじめ、利休以来の茶人と称された鈍翁・益田孝(三井コンツェルンの設立者で男爵)によってはじめられ、特に白雲洞は、翁の創案になる田舎家の席として貴重な茶室とされています。 大正11年(1922)、この茶苑は三渓・原富太郎(横浜の富豪で美術品収集家として著名)に譲られ、この時三渓はあらたに対字斎を増築しました。 昭和15年(1940)、茶苑は再び原家より耳庵松永安左衛門(電力界の重鎮、松永コレクション創設者)に贈られ、こうして茶室は、明治・大正・昭和と3代を代表する3人の茶人の間に伝えられてきたものです。

近代数奇者茶人の間に流行した「田舎家の席」の」先駆的な作例で、山あいに農家の古材の持ち味を生かしながら、八畳敷の茶室を構成しています。 「いろり」に縁無しの畳という意匠は、ここで用いられる茶道具の見立てに、全く枠をはずし、自由なものにしました。床柱は、松永耳庵時代のもので、千年 を経た奈良当麻寺で使われていた古材です。
 お軸
お軸
 茶席ご観料(内部ご見学料)・点茶券付き(お菓子とも) 500円
茶席ご観料(内部ご見学料)・点茶券付き(お菓子とも) 500円

茶室は襖も空いていて、ほとんど外っという感じだったのですが
お席の毛氈の下にホットカーペットが敷いてあり
じっと座っているとじ〜んわりと暖かさが伝わってきてほっこりとしました。
 対字斎(居堂を兼ねた茶室)
対字斎(居堂を兼ねた茶室)
二代目の庵主、三渓原富太郎の作った席で、広縁の正面に「大文字山」の大の字が望まれ、鈍翁筆の対字斎の額がかかげられています。八畳に四畳の立水屋が付属します。
明治年間から開始された箱根登山鉄道(当時は小田原電気鉄道)による強羅地区の開発には、三井物産・益田鈍翁の絶大な協力がありました。 時の社長・草郷清四郎は強羅公園が完成した大正3年(1914)この恩に報いるため園内に翁の好む景勝の地を提供し、翁はここに奇岩を活用した浴室、白鹿 湯と野趣に満ちた茶室二庵をいとなみました。大正11年(1922)鈍翁はかねてより交流のあった原三渓にこの茶室を譲り、三渓はここに対字斎を新造しました。 三渓が逝った翌昭和15年(1940)三渓未亡人の希望によりこれら三席は松永耳庵に贈られ、これにより鈍翁・三渓・耳庵という偉大な茶人であり、明治・ 大正・昭和の日本経済に大きな役割を果たした稀代の経済人たちの遺構がここ強羅公園に現存することになりました。
(強羅公園・白雲洞HPより)
 強羅公園のシンボルともいえる噴水
強羅公園のシンボルともいえる噴水
雪景色の公園も素敵です。
庭園散策ですっかり身体も冷えきってしまったので、ここらで喫茶店へ

 Cafe Pic店内
Cafe Pic店内
 かぼちゃスープ
かぼちゃスープ
暖かいスープを頂きました。
 強羅のお土産に石川菓子舗さんの「強羅もち」
強羅のお土産に石川菓子舗さんの「強羅もち」

柚子の香りが効いて、とても美味しいお菓子でした

お餅の中の黒いもの。お豆のように見えますが小さくきざんだ羊羹でした。
そのあとはお近くの富士屋ホテルへ
 富士屋ホテル・花御殿
富士屋ホテル・花御殿
 富士屋ホテル・本館
富士屋ホテル・本館

富士屋ホテルは・・・
明治11年(1878年)7月15日、日本で始めての本格的なリゾートホテルとして開業しました。
多くの方が、ホテルの名前を聞いて最初に思い浮かぶのが「富士山」でしょう。残念ながら、ホテルから富士山を見ることは出来ません。しかし、富士山が外国人にとっての美の象徴であることを受け、かつてこの地で500年もの歴史を持っていた温泉旅館「藤屋」の名前をもとに「富士屋ホテル」と名付けられました。
明治16年の宮ノ下大火により、ホテルの原形とともに、6年間の記録も失われました。
しかしその1年後には見事に復興を果たし、今も変わらず、箱根に流れる時を見守り続けています。
よくテレビでも紹介されるところなので、一度訪れてみたかった場所です

 ホテルフロントでお出迎えしてくれたオリジナルテディベア
ホテルフロントでお出迎えしてくれたオリジナルテディベア
富士屋ホテル創業130周年を記念して作られたホテルの新しいマスコット

富士屋ホテルのベルボーイの制服を着用した愛らしいテディベアなんだそうです。
帽子、ベスト、ネクタイまで、すべて本物の制服を忠実に再現してあり、脱着が可能な可愛らしいぬいぐるみでした。
 フロント前の様子
フロント前の様子

ロビーへと向かう階段を上がると目に飛び込んでくるのが、なんとも印象的な飴色に磨かれた大階段。その横には、こちらも見事な一枚板の大きな彫刻があります。
実は、ここはかつてフロントカウンターがあった場所で、 この彫刻は、源頼朝が富士の巻狩りを興じる様子を描いたもので、細部まで見事に表現されています。
そして上を見上げると、柱には白い尾長鶏の彫刻が。かつてご来館されたヘレンケラー氏とともに写真に納まったこともある、富士屋ホテルの人気者でした。現在は彫刻となり、ホテルを見守り続けてくれています。
どれもはっとする程素晴らしいものばかりで目を奪われました

 ランチはレストラン「ザ・フジヤ」にて
ランチはレストラン「ザ・フジヤ」にて

(お店のHP掲載のレストラン全景
 )
)

素晴らしい彫刻の数々に格天井、天井下の無数の絵画。
80年間変わらないクラシカルな空間が広がります

足元へ目を移すと何やら不思議なものが・・・

「トーテムポール???」かと思ってしまいましたが(^_^;)
こちら3代目・山口正造さんのお顔を模したレリーフが掘り込まれています。
この「ザ・フジヤ」への思い入れが強く、更にスタッフへの教育にも熱心だった正造さんが、スタッフがきちんと働いているか見張っているとも言われているのだとか

全ての柱の下に刻まれていました。
ランチタイムに大人気の「ビーフカレー」を頂きました。
 まずはピクルス
まずはピクルス
箱根伝統工芸の寄木細工で作られた専用の器にピクルスなど6種類が盛られていました。
付け合せもどれも美味
 さすがは天下の富士屋ホテルです。
さすがは天下の富士屋ホテルです。 ビーフカレー
ビーフカレー
ご飯にかけて、いっただきまーす。


とってもフルーティーなコクのあるお味でした

優雅なランチタイムを満喫いたしました。
伝統ある富士屋ホテルを堪能したあとは御殿場方面へ

晴天でしたので美しい富士山の眺めに期待していましたが、
このようにあいにく雲がかかってました〜


でもお買いものをしていたら段々に雲も流れていき

夕暮れ時にはこんなに素晴らしい光景に


もう少し長居したかったのですが、夜は予定があったため早めに切り上げ。
また是非遊びに行けたらと思います。